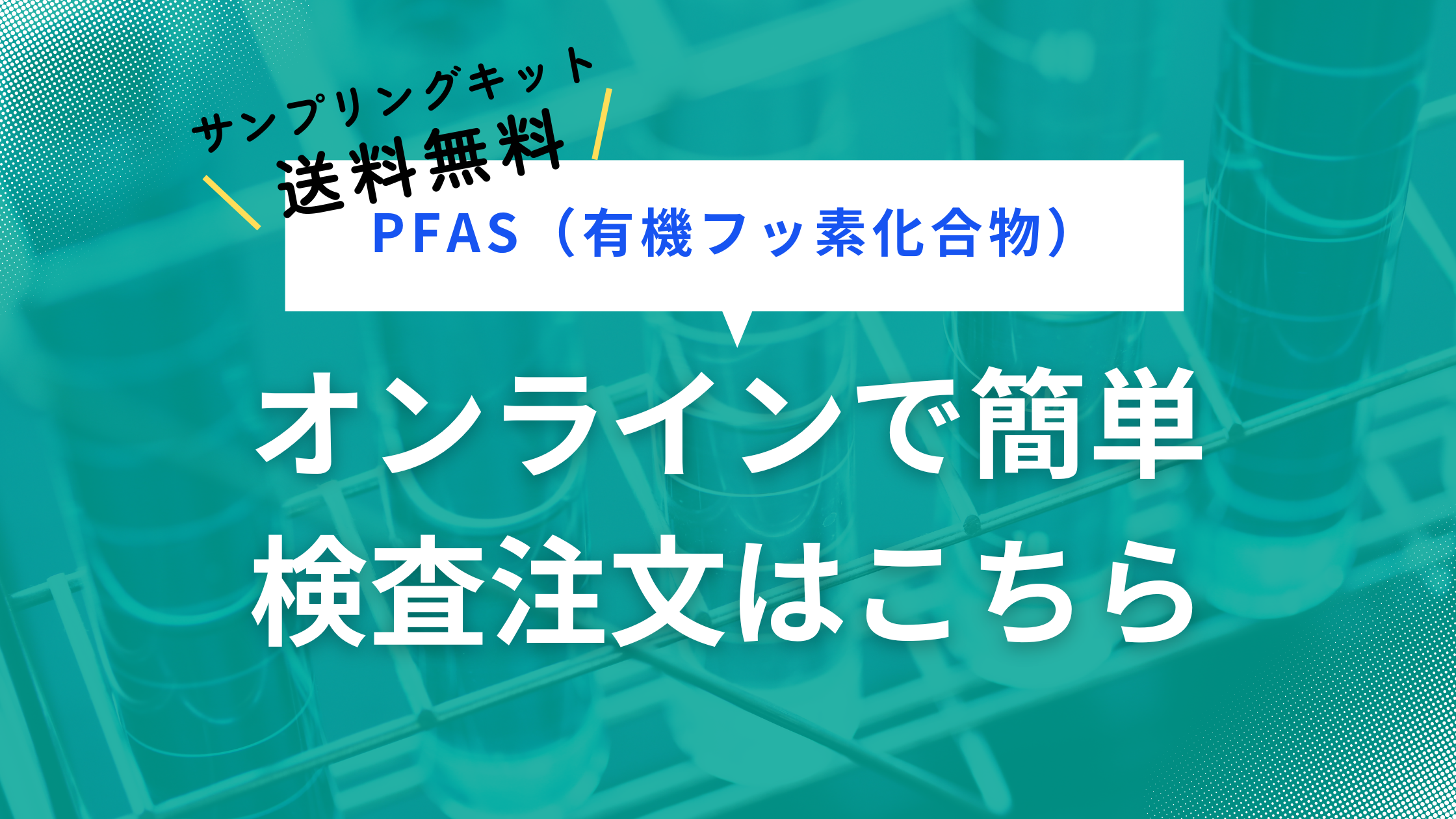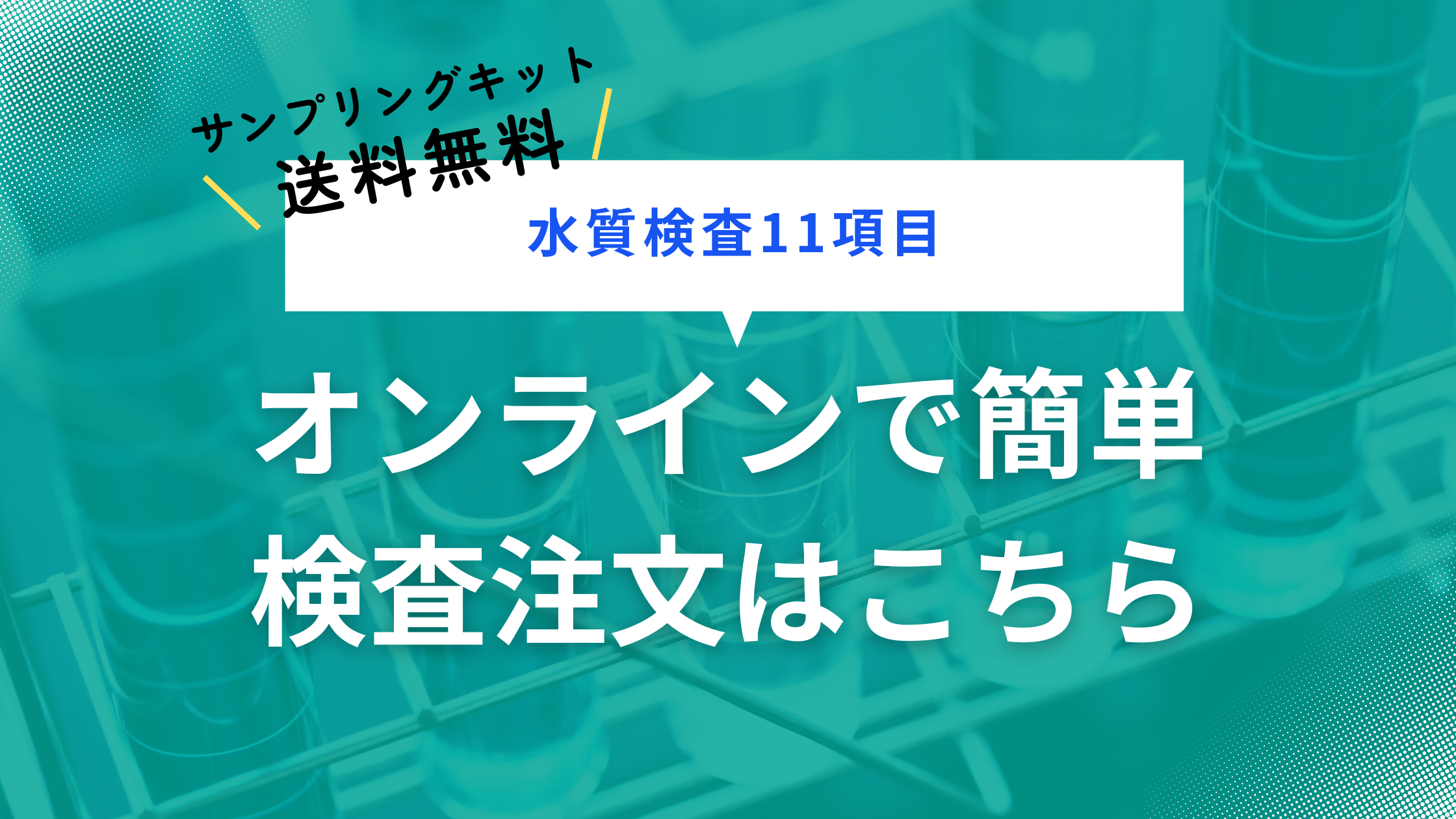「見た目がきれいだから、井戸水の水質検査は必要ない」と判断している方も多いのではないでしょうか。しかし、一見きれいな井戸水であっても、私たちが見えないところで汚染されている可能性があります。
井戸水の水質検査は義務ではありませんが、水道法には水質基準が規定されています。水質基準以上の細菌が混入した井戸水を長年飲用すると、人体への悪影響が懸念されるため、大変危険なのです。
そこで本記事では、井戸水の水質検査が必要な理由から、具体的な検査方法、そして検査を行う上の注意点まで、詳しく解説します。 安心・安全に井戸水を利用するためにも、ぜひ最後までご覧ください。
目次
井戸水の水質検査は義務なのか?
井戸水の水質検査には、法的な義務はあるのでしょうか。結論からお伝えすると、個人が使用する井戸水に関して、法律上の検査義務はありません。しかし、安全な水質を保つためには、定期的な水質検査が強く推奨されています。まずは、水質検査が推奨される理由を解説していきます。
個人の飲用井戸水に検査義務はないが年1回の検査が推奨されている
先述のとおり、個人の飲用井戸水に法律上の検査義務はありません。しかし、井戸水の安全確保は、井戸の設置者自身の責任です。
井戸水の水質には、周辺環境の変化や季節、天候などによって影響を受けやすいという特性があります。例えば、梅雨の時期には集中豪雨により、地中の汚染物質が井戸水に流れ込むケースも考えられるでしょう。
厚生労働省の「飲用井戸等衛生対策要領」では、飲用井戸水の水質検査を推奨しており、年に1回以上は水質検査を行うことが望ましいとされています。また、水に異常を認めた場合には、臨時の水質検査を行うべきと明記されています。
一方、学校や事業所などで使われる「専用水道」に該当する井戸水は、水道法による検査義務が生じるため注意が必要です。
井戸水の水質検査が必要な理由
井戸水の水質検査が必要な理由は、次の2つです。
- 浅井戸は周辺環境から水質が変化しやすい
- 水道法には安全な水の基準が定められている
それでは、詳しく見ていきましょう。
浅井戸は周辺環境から水質が変化しやすい
ご家庭で使われる井戸水の多くは、地表に近い浅い層から水をくみ上げる「浅井戸」です。浅井戸の水質には、地中深くからくみ上げる「深井戸」に比べ、周辺環境の影響で水質が変わりやすいという特性があります。
地中の土壌が天然のフィルターの役割を果たしますが、それだけでは万全ではありません。例えば、近くの農地で使われた農薬や、生活排水に含まれる汚染物質が土壌に染み込み、井戸水に混入する可能性があります。また、集中豪雨や地震の際は、地表の不純物が井戸に流れ込むこともあります。 つまり、見た目が透明で、いやな臭いがなくても、知らない間に有害物質が混じっていることも少なくありません。浅井戸を使用している場合は、定期的に水質検査を行い。安全性を確認することが大切です。
水道法には安全な水の基準が定められている
水道法第4条には、安全な水を供給するための厳格な水質基準が定められています。水質基準とは、私たちが日常的に利用する水道水に適用されるものです。この水質基準により、個人が利用する井戸水の安全性を判断する際の目安となります。
水質検査を行わなければ、井戸水に大腸菌群などの細菌が混入している可能性を否定できません。目に見えない細菌や化学物質の存在は、専門的な水質検査でしか確認できないためです。細菌が混入している水を飲むと、下痢や腹痛などの体調不良を引き起こす恐れがあります。 そのため、水道法に定められた水質基準を参考に、定期的な水質検査で井戸水の安全性を確かめることが、自分の健康を守ることにつながるのです。
井戸水の水質検査方法
井戸水の水質を調べる方法として、主に以下の2つが挙げられます。
- 簡易キットを使用する
- 専門機関へ依頼する
それぞれのメリット・デメリットを見ていきましょう。
簡易キットを使用する
自力で井戸水の水質検査を行う場合、簡易キットは手軽な選択肢です。試験紙・液体試薬・デジタル機器タイプなど、さまざまな種類があり、専門機関に依頼するよりも費用を抑えられます。庭の水やりといった飲用以外の用途として、水質の大まかな目安を知りたい場合は、簡易キットで十分なケースがあるでしょう。
一方、簡易キットの最大のデメリットは、測定できる項目が限られており、精度も専門機関の検査には及ばない点です。例えば、目に見えない細菌や、微量の有害物質を見落とす可能性があります。 また、正確な結果を得るためには、採水時の衛生管理が重要です。後述する注意点を守らないと、正しい結果が得られません。以上の点から、簡易キットはあくまでも目安として活用するようにしましょう。特に、飲用として井戸水を使う場合は、より精度が高い専門機関での水質検査をおすすめします。
専門機関へ依頼する
井戸水の水質検査は、専門機関への依頼がもっとも確実で推奨される方法です。専門知識と専用の機器を用いて、多岐にわたる項目を詳細に分析するため、微量の有害物質も見逃しません。
特に近年は、有機フッ素化合物(PFAS)など、新たな有害物質による地下水への影響が懸念されています。これらの有害物質は目に見えず、味や臭いもないため、一般の方が存在に気が付くことは非常に困難です。
専門機関ならば、最新の法改正や科学的知見に対応した、精度の高い水質検査を受けられます。また、正確な採水方法や運搬が行われるため、検査結果の信頼性が高まります。さらに、保管方法についても指示を受けられるのも、専門機関だからこそのメリットといえます。ご家庭の井戸水を飲用として利用する場合は、健康を守るためにも、専門機関による定期的な水質検査を実施しましょう。
井戸水の水質検査を行う際の注意点
井戸水の水質検査をより正確に行うためには、以下のような注意点があります。
- 採水時は異物の混入に注意する
- 年に1回は定期的に検査する
それでは、詳しく見ていきましょう。
採水時は異物の混入に注意する
自分で水質検査の採水を行う場合、正確な結果を得るためには、異物の混入に細心の注意が必要です。わずかな異物や手の細菌が混じるだけでも、検査結果が大きく変わってしまうためです。
例えば、手に付着した細菌が検体に入ってしまうと、本来であれば存在しないはずの菌が検出され、正しい水質評価ができなくなります。この事態を防ぐためには、採水前に石鹸で手の汚れを十分に洗い落とし、清潔な状態にしておきましょう。
また、雨水の混入も避けるべきポイントです。雨水には空気中のちりや微生物が含まれており、これらが井戸水に混ざると、正確な水質評価を妨げてしまいます。そのため、晴れた日に採水を行い、雨水が影響しないようにしましょう。 適切な採水は、井戸水の安全性を把握する上で非常に重要です。
年に1回は定期的に検査する
前述のとおり、井戸水の水質は常に変化する可能性があるため、年に1回の定期的な水質検査が必要です。厚生労働省の「飲用井戸等衛生対策要領」が対象とするのは、水道法などの適用外となる以下のような施設となります。
- 個人住宅や共同住宅の居住者に飲用水を供給する井戸の給水施設
- 官公庁、店舗、工場といった事業所に飲用水を供給する井戸の給水施設
- 水道事業用の水道や専用水道から供給される水のみを水源としている、小規模な受水槽を持つ施設
上記の施設では、法律上の検査義務はなくても、利用者の健康を守るために自主的な水質管理が求められます。定期的に水質検査を行うことで、井戸水の安全性を継続的に確認でき、安心して井戸水を使えるでしょう。
水質検査の流れ
アムコン株式会社では、初めて井戸水の水質検査を検討される方に、分析技術者が丁寧に説明します。水質検査の流れは、以下のとおりです。
| ご相談 | お客様の井戸水の状況やご希望についてお伺い |
| 検査のご依頼 | ご納得いただいた上でご依頼の承諾 |
| サンプリングキット送付※ | 弊社から採水に必要な専用キットを送付 |
| サンプリングの実施※ | お客様ご自身で井戸水を採取 |
| サンプルの返送※ | 採取したサンプルを弊社までご返送 |
| サンプルの到着・検査の実施 | 弊社でサンプルを受領後、最新の設備と専門知識を持つスタッフが高精度な分析を実施 |
| 検査結果報告書送付 | 検査結果をまとめた報告書をメールでお届け (別途送料にて郵送での送付も承ります) |
※東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県のサービス対応エリアであれば、ご希望により弊社の専門スタッフが採水を実施することも可能です。
検査項目がお決まりの場合、オンライン注文でのご依頼も承ります。 なお、検査の内容や項目などによっては、上記と異なる流れとなる場合があります。ご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
井戸水を使用しているお客様からの水質検査に関する質問
井戸水を飲用に用いているお客様から、水質検査について多くのお問い合わせをいただきます。そこで今回は、ご家庭での井戸水の使用に焦点を当て、よくあるご質問にお答えしていきます。
以下の3つは、お問い合わせの中でも1番多く寄せられるご質問です。
井戸水の水質を検査するとき、何を検査すればいいの?
「毎日使う水だけに、水質の状態は気になる!」と思う一方、「どうすればいいか分からない…」というお客様は多くいらっしゃいます。
井戸水を飲用に用いるのであれば、飲用可否試験として実施する「水質検査11項目」が基本的な検査です。この11項目は、水質基準を定めている水道法の中で「給水施設内で汚染の進むおそれがある項目」として定められています。
水道水に限らず、井戸水を飲み水や炊事用、洗面用などの用途に使う場合は、水の状態を確認することが大切です。下記の検査項目すべてが基準に適合していれば、原則として飲用に用いても問題のないレベルといえます。
【飲用可否の目安となる水質検査11項目】
①一般細菌
②大腸菌
③亜硝酸態窒素
④硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
⑤塩化物イオン
⑥有機物等硝酸態窒素[全有機炭素の量(TOC)]
⑦水素イオン濃度(pH値)
⑧味
⑨臭気
⑩色度
⑪濁度
水質検査11項目の他に実施した方が良い検査は?
水質検査の中には、地中や使用している配管などから溶出してくる可能性のある金属類を調べる検査もあります。以下で、金属類の例をご紹介していきます。
【鉄・銅・亜鉛・鉛】
上記4つの金属類は、色水の原因となるものや、給水管・給水設備の配管の内部の劣化で水の中に溶出してくる可能性があるものです。
【その他】
過去に、マンガン ・ カルシウム ・ マグネシウムなどのご依頼をいただいた事例があります。マンガンの場合、地中の岩盤などから溶出し水中に過剰に含まれると、黒い色を付けることがあります。
また、カルシウムやマグネシウムは、水の「硬度」を知ることができる物質です。検査した水が軟水寄りか、硬水寄りかが分かり、渋み・苦みの有無などを判断する目安となります。 これらの金属類の水質検査は、すべての井戸水で検査が必要なわけではありません。お客様の井戸の供給方法や井戸の位置、周辺の環境などをヒアリングさせていただき、影響を及ぼす可能性の有無に応じて、推奨する検査項目や検査料金が変わってきます。
水質検査の必要性は?
井戸水などを含む地下水には、周囲の環境影響を受けやすい性質があります。特に、浅井戸は周囲の影響を受けやすいです。中でも、浅井戸では、近くに畑や工場などがあることにより、農薬・化学肥料・薬品が地下水へ溶出し、汚染が発生する可能性があります。
一方、深井戸の場合、汚染の可能性は低くなりますが、万が一汚染が確認されると、その影響が長引いてしまう可能性があります。また、浅井戸・深井戸が共に滅菌装置を設置していない場合は、細菌による汚染も考えられるでしょう。これらのことから、定期的な水質検査の実施がおすすめです。
水質検査を行うことで、現在の水の状態を「見える化」することができ、汚染にいち早く気づくことができるでしょう。また、年1回という頻度で継続的に検査を行うことにより、安心して使える水の衛生状態を維持・管理することが可能となります。 なお、100人を超える居住者に給水する施設や、人の生活に使われる水の使用量が1日20tを超える場合、延床の面積が3,000㎡を超えるような場合などは、検査項目や検査頻度が異なります。そのため、詳細はアムコン株式会社までお問い合わせください。
まとめ│井戸水の水質検査に関することはお気軽にご相談ください
井戸水の水質検査は法的な義務ではないものの、利用者の健康を守るためには、年に1回以上の定期検査が強く推奨されます。井戸水は見た目がきれいでも、農薬・細菌・PFASなどの目に見えない有害物質で汚染されている可能性があり、特に浅井戸は周辺環境の影響を受けやすいためです。
簡易キットは手軽である一方、検査項目や精度に限界があるため、専門知識と専用設備を持つ専門機関への依頼がもっとも確実で推奨される方法です。専門機関による水質検査により、正確な検査結果を把握でき、飲用水としての安全性が確保され、継続的な水質管理が可能となります。
アムコン株式会社は、1983年から水質検査を実施している「法定登録検査機関」です。長年にわたりお客様の水質への不安をサポートしてきました。
そんなアムコン株式会社では、豊富な実績と確かな技術により、ご家庭の井戸水や水道水に関するお悩みやトラブルを解決いたします。また、全国からの検査依頼にも対応可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。