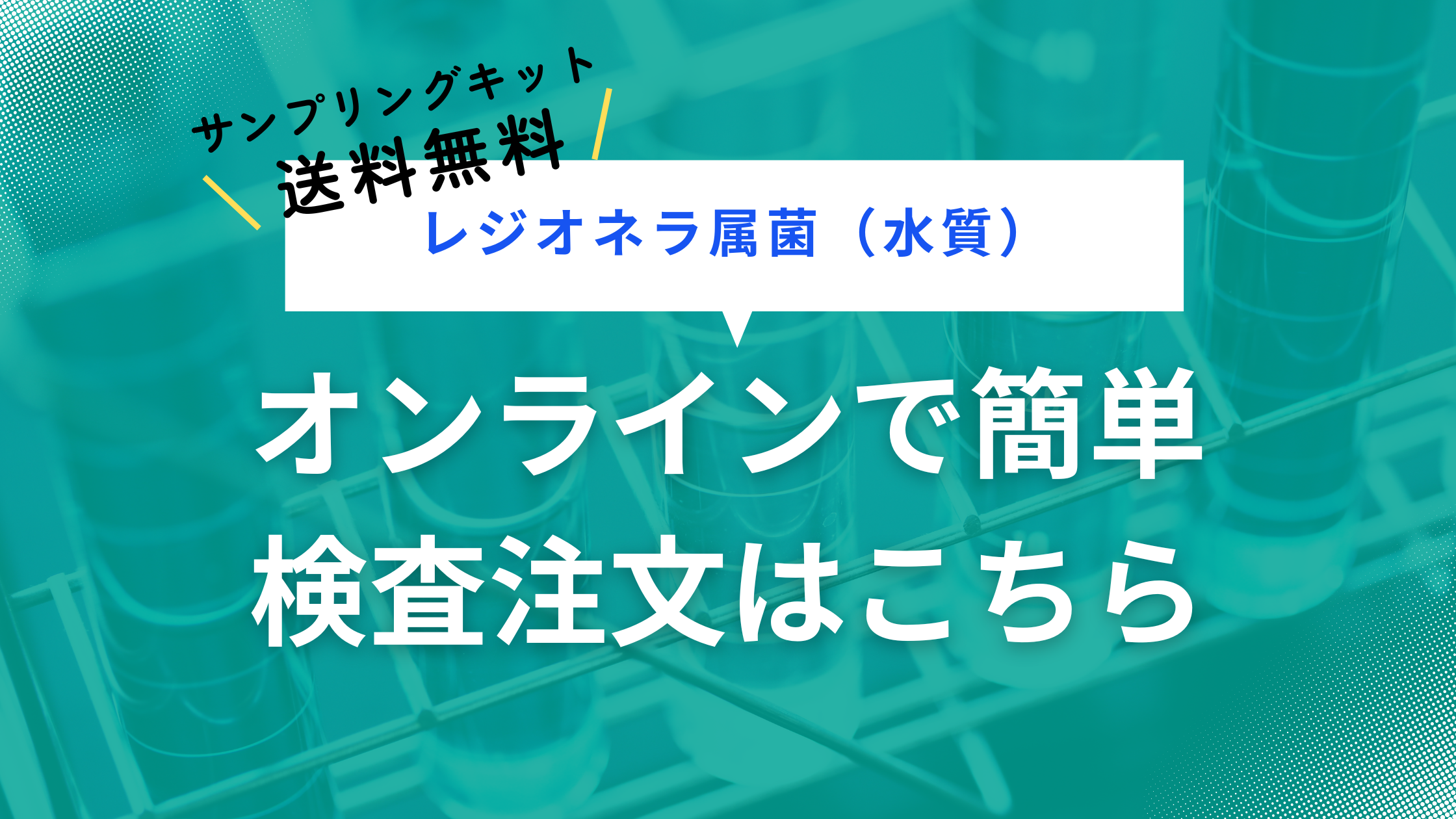「レジオネラ属菌」という言葉を聞いたことはありませんか? ニュースなどで耳にすることはあっても、一体どのような細菌なのか、詳細をよく知らない方も多いでしょう。
レジオネラ属菌は、私たちの身の回りに潜んでおり、感染するとレジオネラ症を引き起こす危険をはらんでいます。特に、循環式の浴槽や冷却塔など、水が滞留する人工的な水環境で繁殖しやすいため、適切な管理が必要です。
そこで本記事では、レジオネラ属菌とは何か、基本情報を分かりやすく解説します。また、感染経路や感染した場合の症状、繁殖させないための方法についても詳しく見ていきます。
この記事を読めば、レジオネラ属菌の正しい知識が身に付き、水質検査の必要性を理解できるはずです。レジオネラ属菌への対策を万全に行えるよう、ぜひ参考にしてください。
目次
レジオネラ属菌とは?
レジオネラ属菌とは、自然界(河川、湖水、温泉や土壌など)に生息している細菌のことで、感染するとレジオネラ症を引き起こしてしまうことがあります。
レジオネラ属菌は、36℃前後の水温が発育至適温度です。
レジオネラ症には主に重症化傾向の強い「レジオネラ肺炎」と軽症型の「ポンティアック熱」の2つの病型があります。国内では感染症法上の四類感染症に分類されており、感染拡大を防ぐために、発生した場合は速やかに届出が義務付けられています。
レジオネラ属菌の感染経路
レジオネラ属菌は、感染経路を正しく理解することが大切です。本来、レジオネラ属菌とは、河川や土壌、水場などの自然界に広く生息する細菌ですが、水が循環したり、長期間停滞したりする施設環境で増殖しやすい特徴があります。
感染経路の中心は「エアロゾル感染」です。レジオネラ属菌の感染は、循環式浴槽や加湿器、冷却塔、給湯施設などにおいて、菌に汚染された細かな霧やしぶき(エアロゾル)を吸い込むことにより、体内に侵入するのが主なルートです。温浴施設やホテルのシャワー、噴水設備、冷却塔など、人工的な水系設備から発生した細かな霧を吸引すると、感染リスクが高まります。
汚染水を誤って吸い込んだり、誤嚥(ごえん)したり、土壌中のレジオネラ属菌が舞い上がった粉じんを吸うことでも、レジオネラ属菌に感染するケースがあります。ただし、レジオネラ属菌はヒトからヒトに直接感染しないため、家族間や同じ施設利用者同士での感染については心配ありません。
レジオネラ属菌は、水環境から発生した目に見えない水滴や、ミストの吸入・誤嚥などを通じて肺に入り、レジオネラ症を引き起こします。予防のためには、設備と水質の衛生管理が重要です。
レジオネラ属菌のリスク
レジオネラ属菌への感染は誰にでも起こり得ますが、特に注意すべきは重症化のリスクです。健康な方が感染しても、軽症で済むことが多い一方、特定の要因を持つ方は、重い肺炎を引き起こす危険性が高まります。
その理由は体の抵抗力、すなわち免疫機能の状態が大きく影響するためです。免疫機能が低下していると、体内に侵入した菌をうまく攻撃・排除できません。結果として、菌が肺の中で増殖してしまい、重篤な症状になりやすくなります。
重症化しやすいのは、免疫機能が未熟な新生児や、加齢により抵抗力が弱まっている高齢者です。また、糖尿病やがんなどの持病をお持ちの方や、透析治療を受けている方も注意しなくてはなりません。さらに、多量の飲酒や喫煙といった生活習慣も、免疫機能を下げるリスク要因とされています。
レジオネラ属菌は、誰にとっても無関係というわけではありません。ご自身やご家族がリスク要因に当てはまる場合は、感染源となり得る水回りの衛生管理など、予防策を意識することが大切です。
レジオネラ症とは
レジオネラ症とは、レジオネラ属菌という細菌が原因で引き起こされる感染症のことです。以下では、レジオネラ症の具体的な症状と、レジオネラ症の発症状況についてご紹介していきます。
レジオネラ症の症状
レジオネラ症には、主に2つの病型があります。重症化する危険性のある「レジオネラ肺炎」と、比較的軽症のインフルエンザに似た「ポンティアック熱」です。原因は同じ菌ですが、症状の重篤度が大きく異なります。
レジオネラ肺炎の潜伏期間は、2~10日ほどです。初期症状は体のだるさや頭痛、食欲不振などですが、次第に悪化していきます。38度以上の高熱や悪寒、胸の痛み、呼吸困難といった肺炎特有の症状が現れるのが特徴です。
また、中枢神経系の症状や、下痢を伴うこともあります。適切な治療が遅れると命に関わるため、迅速な対応が必要です。
一方、ポンティアック熱は、1~2日という短い潜伏期間で発症します。突然の発熱や悪寒、筋肉痛が主な症状で、肺炎の症状は見られません。ほとんどの場合、数日で自然に回復します。 レジオネラ症は、軽症で済むケースから命を脅かすものまで、症状の度合いはさまざまです。特に、高齢者や基礎疾患をお持ちの方は重症化しやすいため、一層の注意が求められます。
レジオネラ症の発症状況
国立感染症研究所の報告によると、2011年第1週から2021年第35週までに集計された症例には、季節性が見られます。レジオネラ症は、年間を通して発生しますが、特に7月・9月・10月に多く、冬季は少ない傾向です。
2011年から2019年にかけては、患者数が増加傾向にありました。一方、2020年は新型コロナウイルス流行の影響で、マスク着用や、温泉施設の利用減少などが功を奏し、前年度よりも患者数が減少しました。年齢別では、高齢者での発症がより多く、肺炎型が大半を占めています。
感染源は水系感染が約3割を占めており、引き続き感染性エアロゾルの発生環境への対策が重要です。
レジオネラ属菌を繁殖させないためには?
レジオネラ属菌の感染経路では主にエアロゾル感染とされていて、エアロゾルを発生させやすい人口環境水が汚染されることで感染源となります。これまでに、冷却塔・温泉・噴水・加湿器・循環式浴槽などが感染源として多数報告されています。
レジオネラ属菌は、20℃以上、特に36℃前後の水が「停滞」または「循環」している環境で高い率での検出が確認されています。また、バイオフィルム [生物膜](※槽内や配管内部、ろ過機内部などを触ったときに感じる“ぬめり”)が形成されると、その中でレジオネラ属菌が増殖してゆき、水が汚染されてしまいます。
バイオフィルムは、消毒剤が浸透していかない特性を持っているため、物理的に除去する必要があります。
このような背景から、レジオネラ属菌を繁殖させないためには、「水を停滞させない」「定期的に清掃を行う」「レジオネラ属菌が繁殖していないか検査で確認する」ことが大切になります。
以下では、レジオネラ属菌を繁殖させないために、公衆浴場でレジオネラ属菌の検査が必要な理由と、検査頻度を解説していきます。
レジオネラ属菌の検査が必要な理由
公衆浴場では、利用者の安全を守るため、定期的な水質検査が義務付けられています。厚生労働省が定める「公衆浴場における水質基準等に関する指針」では、レジオネラ属菌について次の基準を設定しています。
【水質基準】
レジオネラ属菌は、検出されないこと(10cfu/100mL未満)
この水質基準は、レジオネラ症の感染リスクを最小限に抑えるために設けられました。レジオネラ属菌は目に見えない細菌であり、感染すると重篤な症状を引き起こす可能性があります。
そのため、定期検査によって菌の存在を確認し、適切な対策を講じることが必要です。検査を怠ると、知らない間に菌が繁殖し、利用者の健康被害につながる恐れがあります。
レジオネラ属菌の検査頻度
公衆浴場の水質検査は、浴槽の運用形態に応じて実施頻度が定められています。適切な検査間隔を守ることにより、レジオネラ菌の繁殖を早期発見できるのです。
【検査頻度の基準】
- 原湯(水)や上がり用湯(水)など:年1回以上
- 浴槽水
・ろ過器を使用していない、および毎日完全換水:年1回以上
・連日使用:年2回以上(塩素消毒でない場合は年4回以上)
検査結果は3年間の保管が義務付けられており、衛生管理の証拠として重要な役割を果たします。日常の衛生管理を怠った結果、事故が発生した場合は、営業停止処分や法的責任を問われるリスクがあります。
定期検査は、施設運営者にとって必要不可欠な業務といえるでしょう。検査によって安全性を確認することが、利用者の健康を守る第一歩です。
レジオネラ症 感染危険因子のスコア化
感染危険因子のスコア化とは、レジオネラ症に対する危険度を、①菌の増殖とエアロゾル化(空気中への飛散)、②吸入危険度、③人の感受性の3要因でスコア化したものです。
このスコアは感染危険度の目安であり、絶対的な安全性や危険性を示すものではありませんが、この危険度を可能な限り減少させるよう、スコアを参考に対応することが重要です。
感染危険因子の点数化
感染危険因子の軽重を考察し、下記のように点数で表します。
①菌の増殖とエアロゾル化の要因(1~3点)
- 給湯水など…1点
- 浴槽水、シャワー水、水景用水など…2点
- 冷却塔水、循環式浴槽水など…3点
②環境・吸入危険度(1~3点)
- 開放的環境(屋外など)…1点
- 閉鎖的環境(屋内など)…2点
- エアロゾル吸入の危険が高い環境…3点
③人側の要因(1~3点)
- 健常人…1点
- 喫煙者、慢性呼吸器疾患患者、高齢者、乳児など…2点
- 臓器移植後の人、白血球減少患者、免疫不全患者など…3点
具体例1
娯楽施設における給湯設備。蛇口は屋内にあり、乳幼児から高齢者までが手洗い、飲水などに使用。
感染危険因子スコア ① 1点、② 2点、③ 2点 計5点
具体例2
循環式浴槽を使用している浴場施設。屋内施設ではあるが、エアロゾル吸入の可能性は否定できない環境にあり。入浴者は乳幼児から高齢者まで多彩。
感染危険因子スコア ① 3点、② 2点、③ 2点 計7点
具体例3
病院屋上に設置された冷却塔。冷却塔と外気取り入れ口が接近しており、気流の影響でエアロゾルが外気取り入れ口に流れ込む可能性がある。入院患者には臓器移植を受けた人なども含まれている。
感染危険因子スコア ① 3点、② 3点、③ 3点 計9点
スコアに基づく対応
以下では、推奨されるスコアの合計点に基づく細菌検査の対応等と、レジオネラ属菌が検出されたときの対応を見ていきます。
(1)推奨される細菌検査の対応等(スコアの合計点に基づく)
①5点以下:常に設備の適切な維持管理に心がける。必要に応じて細菌検査を実施する。
②6~7点:常に設備の適切な維持管理に心がける。1年に最低1回の細菌検査を実施する。水系設備の再稼働時には細菌検査を実施する。
③8~9点:常に設備の適切な維持管理に心がける。1年に最低2回の細菌検査を実施する。水系設備の再稼働時には細菌検査を実施する。
(2)レジオネラ属菌が検出されたときの対応
(ア)エアロゾルを直接吸引する可能性の低い人口環境水
100CFU/100mL以上のレジオネラ属菌が検出された場合には、直ちに菌数を減少させるため、清掃、消毒等の対策を講じる。また、対策実施後は、検出菌数が検出限界以下(10CFU/100mL未満)であることを確認する。
(イ)人がエアロゾルを直接吸引する恐れのあるもの(浴槽水、シャワー水等)
レジオネラ属菌数の目安値を10CFU/100mL未満とする。レジオネラ属菌が検出された場合には、前項と同様に対処する。
<留意事項>
・点数化はあくまでも目安(参考)として提示するものである。実際の管理は個々の水系施設の状況に応じて施設管理者の判断に委ねられている。
・すべての因子を細かく取り上げ点数化することは現実的ではなく、また、すべての人を対象にする場合には絶対的な点数化は不可能である。
・活用に際しては、可能性が否定できない、あるいは危険度に幅が認められる場合には、高い危険度点数で評価し対応することが望まれる。
まとめ│レジオネラ属菌検査にも対応しています
レジオネラ属菌は、循環式浴槽や冷却塔、加湿器など、水が停滞・循環する人工的な水環境で増殖しやすく、エアロゾル(微細な水滴)の吸入を通じて感染します。公衆浴場では、利用者の安全確保のため「レジオネラ属菌は検出されないこと(10cfu/100mL未満)」と、水質基準が設けられています。
また、運用形態に応じた定期的な水質検査が義務付けられています。施設の種類や利用者の特性に応じた「感染危険因子のスコア化」に基づき、適切な検査頻度で菌の有無を確認することが推奨されます。定期的な水質検査は、菌汚染の早期発見と健康被害防止に必要なのです。
ご家庭や施設のレジオネラ属菌対策は、利用者の安全と事業の信頼性維持に直結します。弊社は、レジオネラ属菌検査に対応しており、お客さまの適切な水質管理をサポートいたします。検査に関するご相談やご依頼など、ぜひお気軽にお問い合わせください。