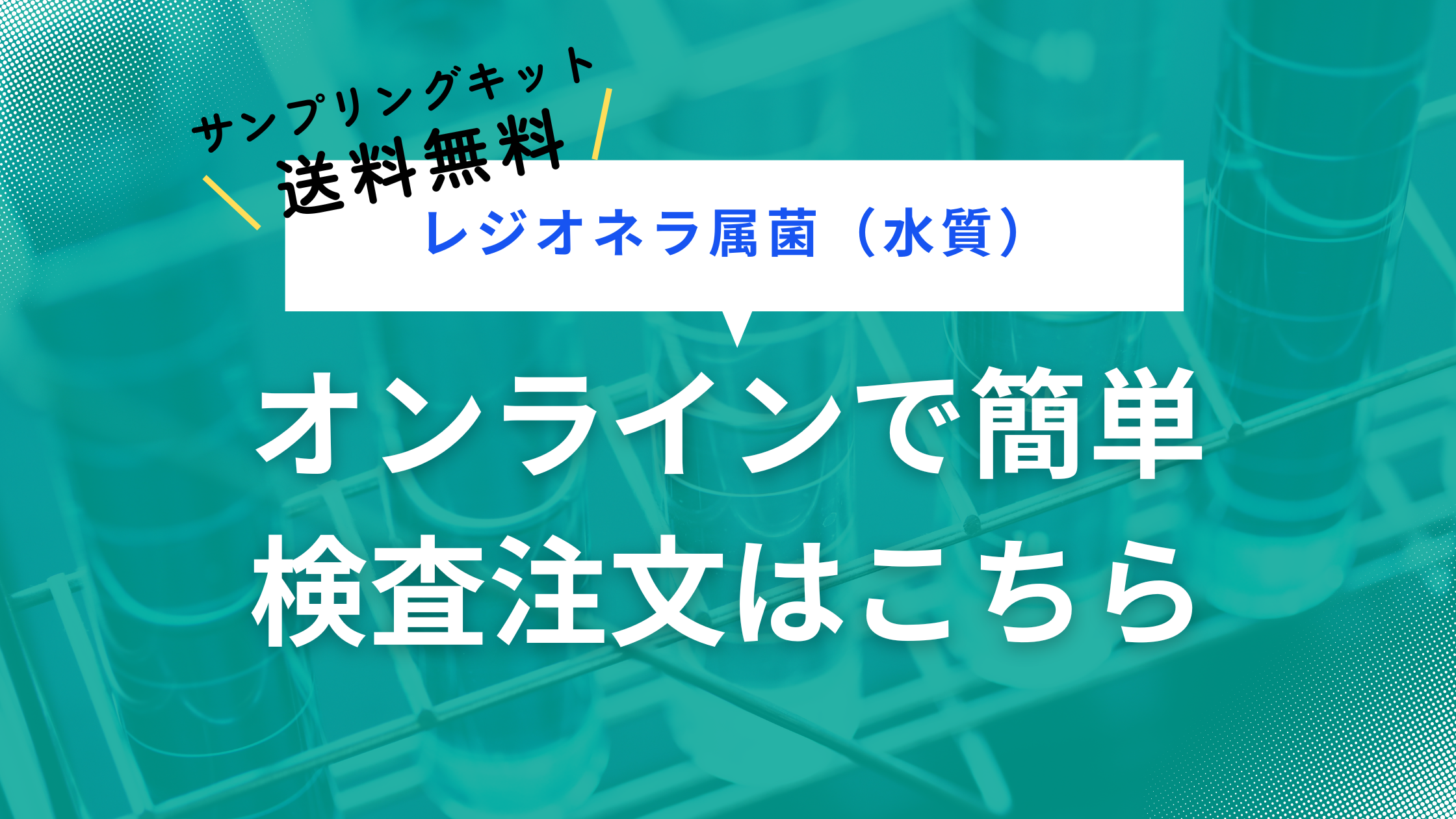温泉など公衆浴場の衛生状態が気になって、入浴をためらったことはありませんか?ぬめりがあったり濁って見えることから「温泉は汚い」というイメージを持っている方も少なくないでしょう。実は、多くの温泉施設や公衆浴場では、法律に基づいた厳格な衛生管理が行われています。
なぜなら、不適切な水質管理は利用者の健康に深刻な影響を与える可能性があるからです。特に、レジオネラ属菌などによる感染症を引き起こすと重大な問題になります。
この記事では、温泉施設や公衆浴場における水質管理と、法律で定められた基準について詳しく解説します。記事を読むと、施設管理者には上記の基準を順守し、利用者の健康を守る責任があることが分かるでしょう。
目次
温泉施設の衛生管理の実態:「温泉は汚い」は誤解?
温泉施設の衛生管理を次の3つの視点から見ていきます。
- ①源泉掛け流しと循環ろ過の違い
- ②法律で定められた水質基準とその意義
- ③温泉施設における日常的な衛生管理の取り組み
以下で詳しく説明します。
①源泉掛け流しと循環ろ過の違い
温泉施設の衛生管理を考える上で、まず理解しておきたいのが源泉掛け流しと循環ろ過の違いです。「源泉かけ流し」は、湧き出た温泉水をそのまま浴槽に注ぎ入れ、使われた湯は排水されます。常に新鮮な湯が供給されるこの方式は、一般的に衛生的と考えられています。一方で、温度や成分が安定しづらいという課題もあります。
「循環ろ過方式」は、浴槽の湯をろ過装置で浄化し、再び浴槽に戻す方式です。ろ過によって湯の中の汚れや不純物が取り除かれるため、ろ過装置の洗浄や浴槽水の完全換水などの管理が適切であれば常に清潔な状態を保つことが可能です。また、温度や成分も安定しやすいというメリットがあります。
重要なのは、どちらの方式であっても、適切な清掃・メンテナンス・定期的な水質検査が行われているかどうかです。源泉かけ流しであっても、浴槽内に汚れが蓄積することがありますし、循環ろ過であっても管理が行き届いていれば非常に衛生的な状態を保つことができます。
方式の違いよりもその施設がどれだけ衛生管理に取り組んでいるかに注目してみるとよいでしょう。
②法律で定められた水質基準とその意義
温泉施設など公衆浴場の水質管理は、公衆浴場法や各自治体の条例によって厳しく規制されています。これらの法律で定められた水質基準は、利用者の健康と安全を守るために設けられたものです。
お風呂に使用される水の種類により検査する項目は異なり、 検査が必要なお風呂の水の種類には、下記のようなものがあります。
- 原湯…浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される「温水」
- 原水…原湯の原料に用いる水、および浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される「水」
- 上がり用湯…洗い場、およびシャワーに備え付けられた湯栓から供給される「温水」
- 上がり用水…洗い場、およびシャワーに備え付けられた水栓から供給される「水」
- 浴槽水…浴槽内の「温水」や水風呂浴槽内の「水」
■原湯(水)や上がり用湯(水)の場合
色度、濁度、pH値、有機物[全有機炭素(TOC)の量]または過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌、レジオネラ属菌
■浴槽水の場合
濁度、有機物[全有機炭素(TOC)の量]または過マンガン酸カリウム消費量、大腸菌(大腸菌群)、レジオネラ属菌
例えば、水の濁り具合を表し、衛生状態の指標となる濁度は2度以下と定められています。有機物量は、TOC(全有機炭素)の量または過マンガン酸カリウム消費量で測定され、水中の汚染度の指標です。レジオネラ属菌は検出されないこと(10cfu/100mL未満)などが求められます。これらの要素を総合的に評価して、風呂水の安全性が確保されています。
基準値の詳細はこちらをご確認ください。
※温泉水では、その泉質により基準値に当てはまらない場合があります。
これらの基準を順守することで、「温泉は汚い」というイメージとは裏腹に、多くの施設では安全で衛生的な入浴環境が維持されているのです。
③温泉施設における日常的な衛生管理の取り組み
温泉施設では、法律で定められた基準を満たすために、日々さまざまな衛生管理の取り組みが行われています。これらの取り組みは、「温泉は汚いのでは?」という誤解を払拭するものです。
例えば、浴槽の清掃と定期的な消毒の実施が挙げられます。多くの施設では、営業終了後に浴槽の湯を抜き、洗剤で洗浄し、消毒を行っています。また、原湯を高温維持する方法や、浴槽水の塩素濃度を定期的に測定し、適切な濃度を維持する方法で、細菌の繁殖を抑制するよう管理しています。
循環ろ過システムを使用している施設では、ろ過器の逆洗浄や消毒の実施も重要な取り組み項目です。ろ過器の逆洗浄や消毒の実施により、ろ過器内部に蓄積した汚れや微生物を効果的に除去しています。
さらに、前述のとおり定期的な水質検査を実施し、結果を記録・保管しています。定期的な水質検査の実施は、水質の変化を早期に発見できるため迅速な対応が可能です。 上記の取り組みにより、温泉施設の衛生状態は常に高いレベルで維持されているのです。
公衆浴場の衛生管理の現状:「温泉は汚い」といわれるが、公衆浴場全体ではどうでしょうか?
ここでは、公衆浴場の衛生管理の現状について紹介します。
- ①公衆浴場法に基づく清掃・消毒の頻度
- ②浴場設備の衛生管理における課題と対策
- ③利用者の衛生意識向上への取り組み
以下で順番に見ていきましょう。
①公衆浴場法に基づく清掃・消毒の頻度
公衆浴場法では、浴槽水の清掃・消毒について具体的な頻度が定められています。これらの規定は、安全で衛生的な入浴環境を確保するためのものです。
公衆浴場では、浴槽水の完全換水および清掃は原則として毎日行うことが求められています。ただし、連日使用型の循環ろ過装置を導入している場合は、一定の衛生基準を満たしていることを前提に、週に1回以上の頻度での完全換水・清掃でも認められています。詳細は各自治体の条例に基づいて管理されるため、施設ごとの確認が必要です。
消毒については、塩素系薬剤を使用する場合、遊離残留塩素濃度を頻繁に測定し、常に0.4mg/L以上に保つことが求められています。また、遊離塩素でなく結合塩素の塩素系消毒として、モノクロラミン消毒法を採用している場合は、3mg/L程度の濃度を維持するのが一般的です。(温泉の泉質によってはイソシアヌル酸で消毒しており、この場合の検査項目は有機物[全有機炭素(TOC)の量]ではなく、過マンガン酸カリウム消費量になります)
清掃・消毒作業は、専門の清掃スタッフによって実施されています。その結果、多くの公衆浴場では高い衛生水準が維持されているのです。
②浴場設備の衛生管理における課題と対策
浴場設備の衛生管理には、いくつかの課題があります。これらの課題に適切に対処することで、「温泉は汚い」という認識の改善が可能です。
1つ目の課題は、浴槽や配管内のバイオフィルム形成です。バイオフィルムは、微生物が分泌する粘着性物質で覆われた集合体で、消毒剤への耐性が高くなります。これに対しては、定期的な物理的洗浄や適切な濃度での消毒剤使用が効果的です。
2つ目は、レジオネラ属菌の増殖リスクです。これらの菌は、36℃前後の温度域で増殖しやすく、バイオフィルムが形成されるとその中でレジオネラ属菌が増殖していきます。対策として「水を停滞させない」、「定期的な高温消毒・清掃を行う」、「レジオネラ属菌の検査を行う」ことが大切になります。
3つ目は、利用者の体から出る有機物の蓄積です。有機物は微生物の栄養源となり、増殖を促進します。そのため適切な浴槽水のろ過が重要です。ヘアーキャッチャーによる清掃も有効です。
③利用者の衛生意識向上への取り組み
公衆浴場の衛生管理において、利用者の協力も大切です。多くの施設では、利用者の衛生意識向上のためのさまざまな取り組みをしています。
最初に入浴前のかけ湯の徹底を呼びかけています。かけ湯は体についた汚れを落とし、浴槽水の汚染を防ぐ行為です。多くの施設では、ポスターなどで注意喚起を行っています。
また、浴槽内での洗髪や石鹸の使用を禁止しています。浴槽内では、浴槽水を著しく汚染する可能性があるためです。この点についても、明確な注意書きを掲示するなどの対策が取られています。
タオルを浴槽に入れることも禁止されています。タオルには雑菌が付着している可能性が高いためです。また、細かい繊維くずは浴槽に沈んでしまい、雑菌が繁殖しやすい環境を作り出します。 施設側と利用者が協力することで、安全で快適な入浴が可能になります。
検査する風呂水の種類:安全性を確保するために
①温泉水と一般の風呂水の違い
温泉水と一般の風呂水では、検査項目や基準値に違いがあります。温泉水は、温泉法に基づいて温泉特有の成分分析が義務付けられています。そして、一般の風呂水も含めて公衆浴場法に基づく検査が必要です。(温泉を利用した公衆浴場では、温泉法と公衆浴場法の両方の適用を受けます。)
温泉水の場合、泉質によって含まれる成分が異なるため、温泉法によりそれぞれの特性に応じた検査が行われます。例えば、硫黄泉では硫化水素の濃度測定が重要です。公衆浴場法では、主に衛生面に焦点を当てた検査が実施されます。
②検査方法とその特徴
風呂水の検査方法には、現場で行う簡易検査と専門機関に依頼する検査があります。簡易検査ではpH試験紙や濁度計などを使用し、すぐに結果が分かるのが特徴です。
専門機関の検査では、採水した試料を分析室で詳細に分析します。この方法では、微量成分の分析やより正確な細菌数の測定が可能です。公衆浴場法で義務付けられている定期的な専門機関の水質検査と、日常的な簡易検査を組み合わせた、継続的な水質管理が不可欠です。
検査項目 :安全な入浴環境を確保するための指標
①水質基準とその背景
公衆浴場の水質基準は、厚生労働省の「公衆浴場における衛生等管理要領」に基づき設定されており、利用者の健康を守るために重要な役割を果たしています。
②検査対象となる微生物とそのリスク
入浴施設での衛生管理において、レジオネラ属菌は最も注意すべき微生物です。この菌は温泉源泉水やシャワー水からも検出された事例があり、循環式の給湯水などからの検出例もあります。レジオネラ属菌は重症肺炎(レジオネラ症)を引き起こし、特に高齢者や免疫力が低下した人には危険です。
さらに、大腸菌(群)や一般細菌も水質の衛生状態を示す重要な指標であり、これらの存在は適切な清掃や消毒が行われているかを判断する基準となります。
③検査結果の活用方法と改善策
検査結果は安全な入浴環境維持のための貴重な資料です。
基準値超過時には、浴槽の完全換水と清掃、循環系統の洗浄・消毒、水質管理方法の見直しを速やかに実施しましょう。検査結果は、設備の性能評価や最適化にも活用できます。定期的に水質検査を行い、検査値を管理することで傾向を知り、異常にいち早く気づくことができます。
検査結果に基づき、循環ろ過装置やヘアーキャッチャーなどの設備を最適化し、必要に応じ設備の改善や更新をしましょう。適切に管理された検査結果を利用者に公開することで、施設の安全性と透明性を示せるのです。 さらに、施設のスタッフへの衛生管理教育に検査結果を活用し、日常的な水質管理の重要性への理解を深める必要があります。
検査頻度:理由と検査結果の保管
ここでは、検査頻度とその理由、検査結果の保管について説明します。
①法令に基づく検査頻度とその理由
検査する風呂水の種類や換水の頻度、消毒の方法により検査頻度が異なります。
- 原湯(水)や上がり用湯(水)などの場合…年に1回以上
- 浴槽水の場合
・ろ過器を使用していない、および毎日完全に換水している浴槽水…年に1回以上
・連日使用している浴槽水…年に2回以上(塩素消毒でない場合は年に4回以上)
法令に基づく水質検査の頻度は、浴槽の種類や使用状況によって異なります。頻度の設定は、各浴槽の特性や水質変化のリスクを考慮して決められており、利用者の安全を確保するためです。
原湯、原水、上がり用湯、上がり用水は年に1回以上の検査が必要です。
一方、浴槽水の検査頻度はより細かく規定されています。ろ過器を使用していないか毎日完全に換水している浴槽水は年に1回以上、連日使用している浴槽水は年に2回以上の検査が求められます。特筆すべきは、塩素以外の消毒方法を用いる浴槽の場合、年に4回以上の検査が必要となる点です。これは塩素消毒に比べて、他の消毒方法では水質の変化が起こりやすいためです。
②検査結果の保管と記録の重要性
水質検査の結果は、検査日から3年間保管することが義務付けられています。これは、長期的な水質傾向の分析や、万が一の事故発生時の原因究明に役立ちます。 検査結果を適切に管理・記録することで、施設の衛生管理への取り組みを証明し、利用者の信頼を得られるでしょう。
清掃が不十分だと繁殖する『レジオネラ属菌』には注意が必要
レジオネラ属菌の特徴などは次の通りです。
- ①レジオネラ属菌の特徴と感染リスク
- ②効果的な予防策
- ③施設管理者が取るべき具体的な対策
以下で詳しく見ていきましょう。
①レジオネラ属菌の特徴と感染リスク
風呂水の検査が必要な項目の中では、特に『レジオネラ属菌』に注意が必要です。
適切に管理しないとレジオネラ属菌が繁殖し、乳幼児や高齢者をはじめ、健康な方でも疲労などで体力の落ちている方が感染します。その結果、レジオネラ症を発症し、ときには死に至る危険性もあります。水中に存在している場合は、0.2 mg/Lの遊離残留塩素に1分間接触させれば殺菌されます。しかし、ろ過器や配管等のバイオフィルム(ぬめり)に生息するアメーバの中にいると、なかなか殺菌されません。
そのため、浴槽やろ過器の定期的な清掃・洗浄や、遊離残留塩素の濃度管理に加え、水質検査で適切に管理されているか確認することが重要です。
露天風呂や打たせ湯の入浴設備を有する施設はレジオネラ属菌の繁殖に適した条件を備えているため、特に注意が必要です。 感染は主に、汚染された水のエアロゾルを吸入することで起こります。適切な水質管理と定期的な検査が、利用者の安全を守る上で欠かせません。
②効果的な予防策
予防策として、浴槽水の適切な塩素濃度管理(通常0.2〜0.4mg/L)が必要です。ただし、温泉の性質によっては塩素系薬剤の効果が弱まる場合があるため注意しましょう。
定期的な配管の洗浄・消毒、水の完全換水も効果的です。バイオフィルムの除去が重要で、菌の繁殖抑制が可能です。さらに、水の完全換水をすることで、菌の増殖防止につながります。 除菌方法としては、塩素系消毒剤の使用や、代替法として紫外線殺菌装置の導入などが挙げられます。
③施設管理者が取るべき具体的な対策
施設管理者は、具体的な対策を講じる必要があります。
定期的な水質検査の実施と結果の記録・保管が基本となるでしょう。
併せて、浴槽水の遊離残留塩素濃度を毎日測定し適切に管理することが重要です。浴槽や循環系統の定期的な清掃・消毒、スタッフへの衛生管理教育も欠かせません。 さらに、利用者へ入浴前のかけ湯の推奨など適切な入浴方法を案内することで、レジオネラ属菌の繁殖リスクを大幅に低減できるのです。
まとめ:温泉の快適な入浴環境を目指して
温泉施設や公衆浴場の衛生管理は、利用者の安全と快適性を確保するために不可欠です。法令に基づいた適切な水質検査の実施と、実施結果の管理・記録が重要です。特にレジオネラ属菌対策には細心の注意を払い、定期的な検査と予防策を実施しましょう。
最新の検査技術や管理システムを積極的に利活用し、常に衛生管理の質を高めていくことが、施設の信頼性向上につながります。また、利用者への適切な情報提供と入浴マナーの啓発も、安全な入浴環境の維持に重要な役割を果たします。
温泉施設や公衆浴場の施設管理者は、これらの取り組みを通じて安全で快適な入浴環境を提供することが求められます。継続的な衛生管理の改善と、利用者との信頼関係の構築により、多くの人々に愛される温泉施設づくりを目指すことが重要です。
そのため、管理されている施設で必要な検査内容、検査箇所、検査頻度をご確認ください。 浴場のある施設(ホテル、旅館、福祉施設、フィットネスクラブなど)は、公衆浴場法や各自治体の条例に基づき、風呂水の検査が必要です。ただし、検査内容などの詳細は施設の利用状況や設備の状態によって異なるため、詳しくお話を伺った上で最適な検査プランをご提案いたします。ぜひ一度、アムコン株式会社までお問い合わせください。