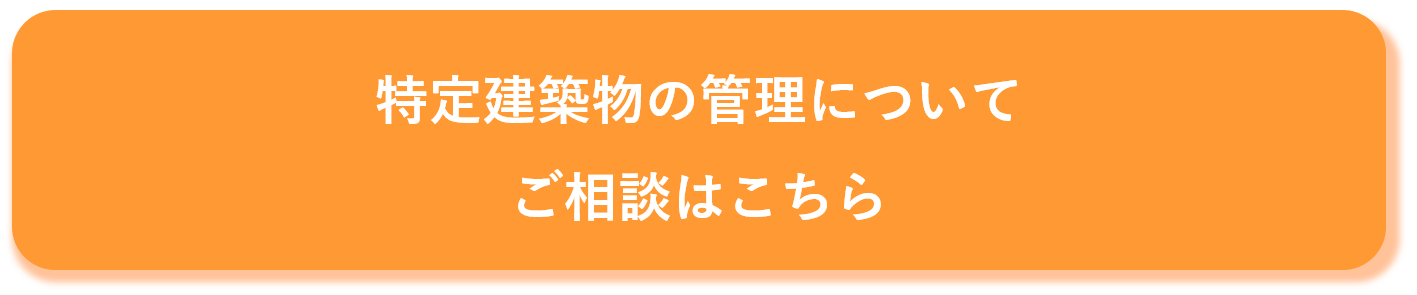特定建築物の基準は、ビル管法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)により、厳格に規定されています。多くの人が利用する建築物では、適切な衛生管理が利用者の健康と安全に直結するためです。
しかし、ビルの衛生管理における法律は、その基準が複雑で理解しにくいものです。
そこで本記事では、ビル管法の対象となる建築物や管理基準について、要点と実務で必要な対応など、詳しく解説します。 ビル管法で規定された管理基準を順守し、ビル管理者を適切に配置するためにも、ぜひ参考にしてください。
目次
ビル管法(ビル管理法)とは?
ビル管法とは「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」が正式名称で、多くの人が利用する建物の衛生的な環境を確保するための法律を指します。
不衛生な環境は、利用者の健康を損なう恐れがあるため、ビル管法で各種基準や項目を規定しているのです。ビル管法の基準項目は、空気環境の調整、給水・排水の管理、定期的な清掃など、多岐に渡ります。また、ねずみや害虫の防除についても、細かく規定されています。 このように、ビル管法は、特定建築物を安全かつ衛生的に保つ上で、重要な役割を担っている法律といえるでしょう。
ビル管法の目的はビルの衛生環境の向上
ビル管法の1番の目的は、公衆衛生の向上と増進です。多くの人が利用する建物には、衛生的な環境を確保することが求められます。
建物内の環境悪化は、利用者の健康被害に直結してしまうため、こうした事態を未然に防ぐことが、ビル管法の大きな目的です。ビル管法には、空気環境や給排水、清掃など6項目の衛生管理基準が設定されています。そして、建物の所有者には、基準に沿った適切な維持管理が義務付けられています。
利用者が1日を通して健康かつ快適に過ごせる環境を守ることが、ビル管法の最も重要な役割なのです。
2022年にビル管法が一部改正
2022年4月1日、ビル管法の一部が改正されました。この改正は、最新の科学的知見や社会情勢の変化を規制に反映させ、利用者の健康を今まで以上に守り、効率的なビル管理を実現するためです。
一部改正では、実態にそぐわない規制の見直しも行われました。具体的には、空気環境基準の一部強化(温度、一酸化炭素)や、建築物環境衛生管理技術者の兼任要件の緩和などです。帳簿書類の電子保存が認められた点も、大きな変更点となっています。 また、直近の法改正によって、より合理的かつ実効性のある衛生管理が可能となりました。
ビル管法の対象は?
ビル管法の対象は、不特定多数の人が利用する「特定建築物」であり、床面積と用途が法令で明確に定められています。以下では、ビル管法の対象の特定建築物を詳しく説明し、届出についても併せて紹介していきます。
ビル管法の対象となる特定建築物
ビル管法の対象は、不特定多数の人が利用する「特定建築物」です。特定建築物とは、多数の人が利用し、用途と延べ床面積が政令によって定められた基準を満たす建物のことです。具体的には、次の用途に供される建築物が該当します。
延べ床面積の基準:以下の用途で3,000平方メートル以上
- 興行場(映画館や劇場)、百貨店、図書館、集会場、美術館、博物館、遊技場、旅館(ホテル)など
- 事務所、店舗
延べ床面積の基準:以下の用途で8,000平方メートル以上
- 学校
対象となる建築物では、利用者の健康と安全を守るため、専門的な知識に基づく衛生管理が義務付けられているのです。
もし、特定建築物に該当するか判断に迷った場合は、管轄の保健所にご相談してください。
一方、ビル管法で対象外の建物は次の2つです。
- 特定の目的のために利用され、不特定多数が常時利用しない建物
- 延べ床面積の基準を満たさない建物
例えば、集合住宅であるマンションや病院、老人ホーム、工場などは、不特定多数が自由に出入りする施設ではないことから、ビル管法の対象外となります。
特定建築物の届出の提出が必要
特定建築物の所有者や管理者は、建物の使用を開始する日から1カ月以内に届出を提出しなければなりません。届出は、特定建築物の所在地を管轄する保健所を経由し、都道府県知事へ提出します。また、保健所を設置する市・特別区では、保健所を経由し、市長・区長あてに提出します。
届出を提出することは、ビル管法で定められた義務です。届出を怠ると、法律違反となるため注意してください。なお、届出には、建築物の名称や所在地、用途、延べ床面積などの情報を記載します。
届出の提出後も、届出事項に変更があった場合や、その建物が特定建築物に該当しなくなった場合は、1カ月以内に届出内容を修正しなければなりません。例えば、用途が変更されたり、大規模な改修によって延べ床面積が変わったりした際には、速やかに届出の再提出が必要です。 適切な届出の手続きと管理は、ビル管法順守の第一歩です。建物の利用者を守るだけでなく、建物の管理者自身の安全と信頼の確保にもつながります。
ビル管法に規定される管理基準
ビル管法に規定される管理基準は、次の5つです。
- 空気環境の調整
- 給水の管理
- 排水の管理
- 清掃
- ねずみや害虫の防除
それでは、詳しく見ていきましょう。
空気環境の調整
ビル管法では、特定建築物の空気環境を快適かつ衛生的に保つため、空気環境の調整に関する基準を定めています。この基準は、利用者の健康を守る上で非常に重要です。空調設備機器は定期的に清掃し、ほこりなどの汚れを除去し、適切に維持管理する必要があります。 空気環境の測定頻度は2カ月以内ごとに1回となっています(ホルムアルデヒドの量は下記のとおり)。
| 項目 | 基準 | 頻度 |
|---|---|---|
| 浮遊粉じんの量 | 0.15 mg/m3以下 | 2ヶ月以内ごとに1回 |
| 一酸化炭素の含有率 | 100万分の6以下 | |
| 二酸化炭素の含有率 | 100万分の1,000以下 | |
| 温度 | 18℃以上28℃以下 | |
| 相対湿度 | 40%以上70%以下 | |
| 気流 | 0.5m/秒以下 | |
| ホルムアルデヒドの量 | 0.1 mg/m3以下(=0.08 ppm以下) | 新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回 |
上記の基準値を満たすことにより、特定建築物内の空気は衛生的に保たれます。定期的な測定と適切な調整が、利用者の健康維持につながるのです。
給水の管理
ビル管法では、特定建築物で供給する水が水道法第4条で定めている水質基準を満たすよう、義務付けられています。利用者の健康を確保するためには、給水の適切な管理が欠かせません。
飲料水の主な措置内容と実施回数は、以下のとおりです。
- 給水栓における遊離残留塩素の含有率保持:0.1mg/L以上に保つよう、7日以内ごとに1回検査する
- 貯水槽の清掃:有害物や汚水による汚染を防ぐため1年以内ごとに1回清掃を実施
- 飲料水の水質検査:定期的に検査し安全を確認する
水道または専用水道のみを水源とする飲料水供給の場合
| 検査回数 | 6ヶ月ごとに1回 | 1年ごとに1回 (6月1日~9月30日) |
| 検査項目 | 水質16項目 | 水質12項目(消毒副生成物12項目) |
- 異常時の検査:給水栓での水の色・濁り・臭い・味などに異常を認めた場合、その都度必要な項目を検査する
- 健康被害のおそれがある場合の対応:飲料水による健康被害の恐れがあることを知った際は、直ちに給水を停止し関係者へ周知を徹底する
上記の定期的な検査や清掃を実施することで、水の安全性を確保し、利用者が安心して水を使える環境を維持しています。また、飲料水のみならず、地下水や雑用水にも基準が定められています。
排水の管理
ビル管法では、特定建築物の排水設備についても、衛生的な管理基準を設けています。基準は、利用者の快適性と健康を守る上で非常に重要です。排水の管理に関する基準では、排水設備の清掃を6カ月以内ごとに1回行うことが規定されています。
排水管の内部には、腐敗した食物くずや油脂、繊維くずなどの汚れが付着し、蓄積されるためです。汚れがたまると、排水管の内部が徐々に狭くなり、最終的には排水管が詰まる原因となります。
また、排水設備に問題があると、排水不良を引き起こしてしまい、悪臭の発生につながります。正常な機能の維持には、定期的に汚れを取り除く排水設備の清掃作業が必要です。さらに、継続的な排水設備の清掃には、排水管の劣化を予防し、設備の寿命を延ばす効果も期待できます。 このように、適切な排水管理は、建物の衛生環境を良好に保つ上で重要なのです。
清掃
ビル管法では、特定建築物内の清掃や、廃棄物処理についても基準を設けています。利用者が快適に過ごし、健康を維持するためには、清掃が不可欠です。特定建築物は、不特定多数の利用者の往来によって土砂やほこりが持ち込まれ、さまざまなごみや汚れがたまりやすいためです。
特定建築物では、建物内の衛生的な環境を常に保つことが求められます。日常的な清掃はもちろんのこと、大掃除は6カ月以内ごとに1回、定期的に実施するよう定められています。建物全体の清潔さを維持し、利用者が気持ち良く施設を利用できる環境を提供できるのは、定期的な清掃による結果なのです。 適切な清掃は、ひいては感染症の予防にもつながり、建物の資産価値維持にも役立つでしょう。
ねずみや害虫の防除
ビル管法では、特定建築物において、人の健康を損なう恐れのあるねずみや害虫の発生・侵入防止、駆除が義務付けられています。害虫の防除は、利用者の安全と快適な環境維持につながる重要な管理項目です。
特に、ねずみの駆除では、薬剤を濫用すると、防除作業者や建物利用者の健康に悪影響が出るリスクがあります。そのため、殺そ剤や殺虫剤を使用する場合は、薬事法上の製造販売承認を得た医薬品、または医薬部外品を利用することが規定されています。
具体的な措置内容と実施回数は、次のとおりです。
- 調査の実施:ねずみなどの発生場所・生息している箇所・侵入する経路・被害状況などについて、6カ月以内ごとに1回、統一的に調査を実施すること
- 発生防止措置:上記の調査結果に基づき、ねずみなどの発生を防止するため、必要な措置をその都度講じること
- 薬剤の使用:殺そ剤や殺虫剤を使用する際は、薬事法の承認を受けた製品を用いること
上記の対策を徹底することにより、特定建築物の所有者や管理者は、特定建築物内の衛生環境を維持し、利用者を守ることができます。
ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)の選任が必須
特定建築物では、ビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)を選任し、管理運営させる必要があります。以下では、建築物環境衛生管理技術者の業務と、ビル管理士資格取得方法を紹介していきます。
建築物環境衛生管理技術者の業務
建築物環境衛生管理技術者の業務は、多岐にわたります。主な業務内容は、以下のとおりです。
| 業務 | 内容 |
|---|---|
| 管理業務計画の立案 | 衛生管理に関する年間計画などを策定 |
| 管理業務の指揮監督 | 清掃や空気環境測定など実際の管理業務を指揮監督 |
| 「建築物環境衛生管理基準」の測定または検査結果の評価 | 空気環境や水質などの測定・検査結果を評価し基準に適合しているか確認 |
| 環境衛生上、維持・管理に必要となる各種調査の実施 | 害虫の発生状況調査など衛生状態を維持するためのさまざまな調査 |
「建築物環境衛生管理技術者」は、特定建築物1つにつき1人を選任することが定められていますが、1人で複数の特定建築物を管理することもできます。また、所有者との間で委任関係などの法律上の関係がある場合、特定建築物に常駐しなくてもよいとされています。
建築物環境衛生管理技術者の国家試験を受験
建築物環境衛生管理技術者の資格取得方法の1つに「国家試験の受験」があります。試験を受けるには、建築物の環境衛生上の維持管理に関する実務経験が必要です。具体的には、空気調和設備や給排水設備などの運転・保守管理業務に対し、2年以上従事した経験のある人が受験資格を得られます。 また、試験は建築物衛生に関する幅広い知識が問われるため、十分な準備が必要です。これらのことから、当資格の保持者は、ビル管法に則った衛生管理を専門的に行うことが可能といえるでしょう。
建築物環境衛生管理技術者の講習会を受講
建築物環境衛生管理技術者の資格は、国家試験を受験するほか、厚生労働大臣が指定する講習会を受講することでも取得できます。この場合は、講習会で試験科目と同様の内容を合計100時間以上学ぶことで、資格を得ることが可能です。
ただし、講習会には、実務経験や学歴、またはすでに保有している資格の内容によって細かく定められた受講資格があります。例えば、特定の学校を卒業している、あるいは特定の業務での実務経験が一定期間あるといった条件が設けられています。 そのため、受講を希望される方は、事前に日本建築衛生管理教育センターで受講資格を確認の上、資格取得を目指しましょう。
まとめ│ビル管法を理解し適切に特定建築物の維持管理をしましょう
ビル管法は、特定建築物の衛生管理基準を明確に定める法律です。利用者の健康・安全の確保、公衆衛生の向上・増進を目的としています。ビル管法では、空気環境や給排水、清掃、ねずみ・害虫防除など、5項目の衛生管理基準を義務付けています。
特定建築物の衛生管理基準について気になる方は、ぜひ弊社までご相談ください。専門知識と実績豊富な分析技術者が、お客様をサポートいたします。